会社に残っても評価されない現実
若い頃はがむしゃらに働き、30代で実績を積み上げ、40代でさらなる成果を出す。
そして50代になれば、部下を育て、会社全体のことを考える立場になる——。
多くの人たちはそんなキャリアパスを思い描いていたかもしれません。
しかし、現実はどうでしょうか。
会社というピラミッド構造の中で、ポストは上に行くほど少なくなり、今となっては同期や後輩との競争も避けられません。
50代に入った今、ここで一度立ち止まり、「会社員としてこのまま生き続けること」に潜むリスクを冷静に直視する必要があるのではないでしょうか。
この年齢に至るまで、私たちは長く会社に貢献してきました。
終身雇用や年功序列といったシステムが崩壊しつつあるとはいえ、今はまだ完全な能力給になっているわけではありませんから、子どもの成長とともに増える学費などを支えるためにも、年功序列による昇給はある種、許容されています。
しかし、企業側から見れば、年齢とともに上がり続けるあなたの給与は、いつしか「コスト」として捉えられるようになりますから、現代において、年齢を重ねることが必ずしも評価につながるとは限らなくなっているのも事実です。
とくに、働きぶりと支払われている給与のバランスが見合わないと判断された場合には、今ある会社での立場は非常に危ういものとなる可能性もあります。
20代や30代の若手が低い給与で生産性の高い働きぶりを見せる一方で、管理業務が増え全体的な仕事量が減ったベテラン社員の高い給与が、果たして妥当なのか。
経営が厳しくなれば、そうしたバランスの良くない人材、つまり、50代前後の社員がリストラの対象となるのは、残念ながら避けられない現実です。
もちろん、社長や役員への道筋が明確に見えているのであれば、問題はありません。
しかし、「万年課長でこの先どうなるのか……」と不安を抱えている人もいるのではないかと思っています。
少子高齢化です。
昭和40年代後半の第2次ベビーブームの世代である50代は層が厚く、その下の世代が少ないという人口構造も、ポストの行き詰まりを加速させます。
能力主義の名のもとに、後輩が上司になるというケースも珍しい話ではありません。
さらに気になるのは、会社から「教育投資の対象外」と見なされてしまう可能性です。
企業は将来性のある若い世代に優先的に教育コストを割くようになり、50代の社員は「これ以上の伸びしろは期待できない」と判断されがちです。
そうなると、定年までの長い期間、飼い殺しのような状態で働き続けることになるかもしれません。
年金制度の先行きも不透明です。この先、定年年齢が70歳、あるいはそれ以上に引き上げられる可能性もあります。
あと15年、もしかしたら20年以上も成長の機会も与えられず、ただ会社にしがみつくだけの人生で本当に良いのでしょうか。
かつて私が在籍していた会社でも、それなりのポストにいた人物が平社員扱いに戻され、飛び込み営業をさせられている姿を目の当たりにしたことがあります。
50代からの転職市場の厳しさ
もし「今の会社がダメなら、転職すればいい」と考えているとしたら、その認識は改めたほうが良さそうです。
とくに50代からの転職は、想像以上に厳しい道のりとなることを覚悟しなければなりません。
前提として、50代を対象とした求人の絶対数が少ないという現実があります。
企業が採用コストや教育の手間を考えたとき、これから長く働いてくれる若い世代を優先するのは当然のことです。
50代で採用しても、定年までの期間は限られており、体力的な不安や新しい環境への適応能力も懸念されてしまいます。
いくら人手不足が叫ばれていても、50代の求人はごくわずかです。
あったとしても大幅な待遇ダウンや、これまでとは全く異なる職種であるケースも少なくありません。
これまでの生活水準を維持したまま転職することは、極めて困難と言わざるを得ないのが現実です。
運良く面接まで進めたとしても、そこには「年齢バイアス」という見えない壁があります。
求人広告では年齢不問をうたっていても、実際の選考では若い応募者が優先されることは暗黙の了解です。
面接官が自分よりもずっと年下で、その相手からまるで値踏みされるかのように質問を受けるという屈辱的な経験をすることもないとはいえません。
書類選考で落とされるならまだしも、面接まで行って不採用が続けば、これまで培ってきた自尊心も大きく傷つくことになります。
そこまでして、慣れない環境に飛び込む覚悟が本当にあるのか、自問自答してみる必要はありそうです。
安直な起業の落とし穴
会社に残るのも厳しい、転職も難しい——。残る選択肢は「起業」です。
しかし、起業すれば誰でも成功できるわけではありません。
むしろ、安直な考えで起業に踏み出し、失敗している人は後を絶たないのが現実です。
会社員経験が長い人ほど、起業後の現実とのギャップに苦しむことがあります。
会社員時代は、与えられた業務範囲だけを考えていればよく、終業後には同僚と飲みに行くような気楽さもありました。
しかし、起業すれば、自分が動かなければ何も進まないという現実に直面します。
常に事業全体のことを考え、次に何をすべきかを自ら判断し、行動し続けなければなりません。
この「思考の癖」を会社員時代のうちに身につけていないと、起業後に立ち行かなくなる可能性が高いのです。
多くの場合、経営の経験のない人が起業する際には、事業の先行きの見通しは甘くなりがちです。
机上の空論で「1日にこれくらいお客さんが来れば、これくらいの売上が……」と皮算用しても、現実はそう甘くはありません。
とくにお店の内装や設備にこだわりすぎて初期投資をかけても、肝心の集客が思うように進まなかったりすれば、あっという間に資金が底をつき、数ヵ月でお店を畳むことになるケースもあります。
考えている以上に、集客が加速するスピードは遅いものです。
まずはいかにキャッシュフローを安定させるかを最優先に考えなければなりません。
ここまでの話で「起業は難しそうだ……」と感じるような人たちが次に目を向けがちなのが、ネットワークビジネス(MLM)やフランチャイズ(FC)です。
簡単に儲かりそうに見えるのだと思います。
たしかに「本部がサポートしてくれるから大丈夫」「加盟すれば成功する」といった甘い言葉に誘われてしまう気持ちもわからなくはありません。
しかし、ネットワークビジネスの実態は、友人・知人を勧誘し続けることで人間関係を壊したり、結局は生活できるほどの収益を得られなかったりする場合がほとんどです。
フランチャイズも、本部は加盟金で儲けるビジネスモデルであることが多くあります。
加盟店オーナーになったとしても人手不足から自身が休みなく働き続け、数年で廃業に追い込まれるケースも見てきました。
高額な起業塾や起業コンサルに頼ろうとする人もいますが、ここでも注意が必要です。
もちろん質の高いコンサルタントや起業塾も存在しますが、残念ながらセールスが上手なだけで、再現性のないノウハウを高額で売りつけ、受講生を食い物にするような「ひよこ食いビジネス」も横行しているのが実情です。
起業コンサルタント自身が、実は起業コンサルで起業したという笑えない話もあります。
どのような道を選択するにしても、忘れてはならないのは、その結果はすべて自己責任であるということです。
自由には、必ず責任が伴います。会社に残るのか、転職するのか、それとも起業するのか——。
どの道を選ぶにしても、情報を鵜呑みにせず、慎重に見極め、覚悟を持って判断することが何よりも重要です。
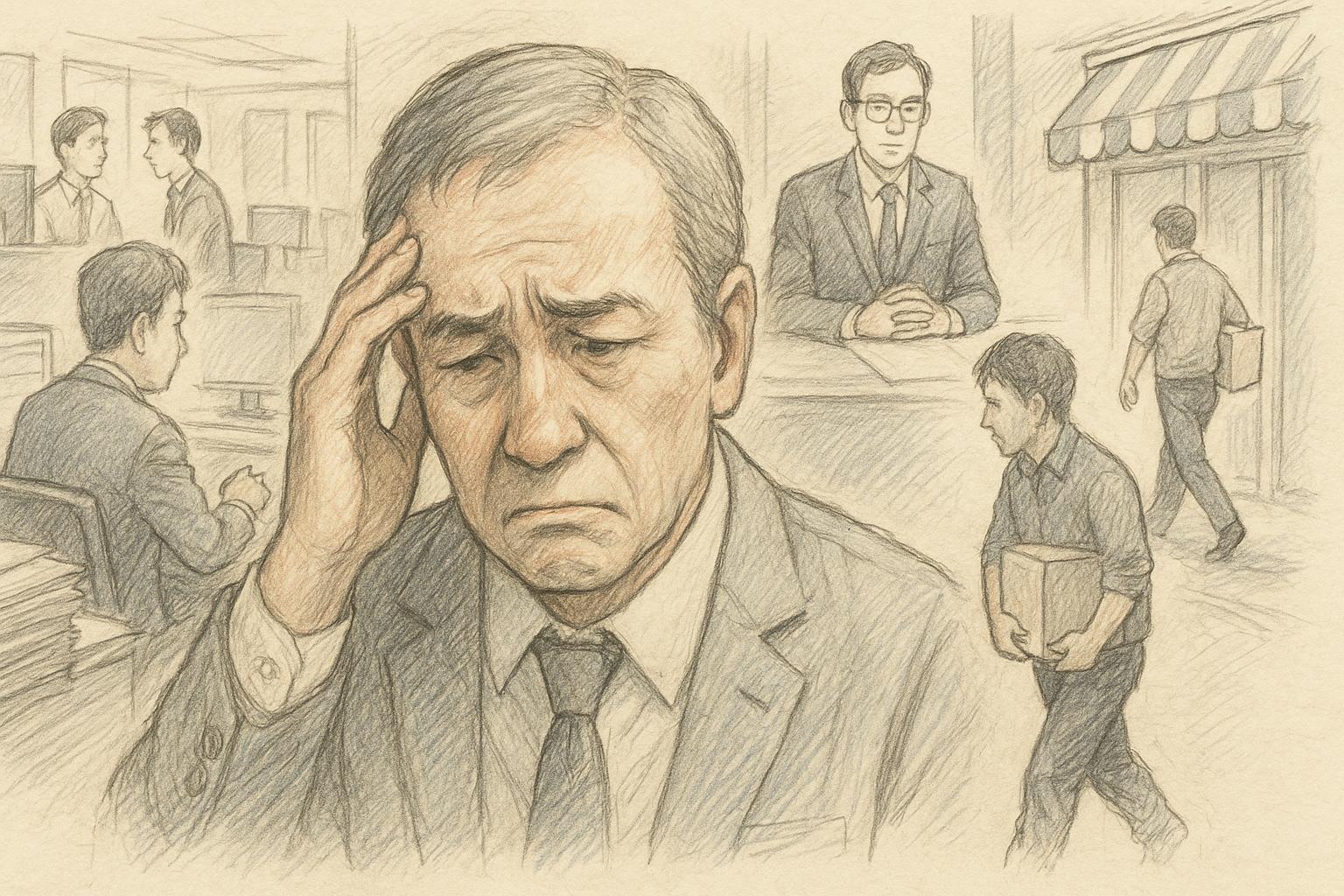


コメント