最後まで読みたくなる原稿構成
Kindle出版をし、めくってもらって収益を上げるには、あなたの出した Kindle本を最後のページまでめくってもらうことが大切です。
50代からの起業でKindle出版をして、めくってもらって収益を上げるには、1冊だいたい約300ページほどのページ数の本に仕上げることを想定しています。
300ページもの長い文章を読者に読み切らせるには、書き出す前にあらかじめ本の構成を作っておくことが大切です。
構成ができていないと、話がいつのまにか横道に逸れてしまったり、書いているうちに何を言いたかったのかを見失ってしまったりすることもあり得ます。
ここからは、300ページになるような長文であっても、読者が飽きずに読み進めたくなる原稿の構成と書き方について解説していきます。
まずは原稿の構成についてです。300ページほどの本を最後まで読ませるには、「あなたのノウハウをどのような順で説明すると読者は再現できるのか」を具体的にした原稿の構成を作ります。
Kindle本を執筆するときの道しるべになるように、原稿でノウハウを説明する内容を10項目にして順に並べました。
Kindleの原稿でノウハウを説明する順番
- そのノウハウを身につけた経緯は何か
- ノウハウを実践して、得られるものは何か
- そのノウハウのメリット、その根拠や理由
- そのノウハウの全体像
- そのノウハウを実行するための前提条件や必要な準備について
- まず何から取り掛かればいいのか
- 次に何をすればいいのか
- 最後に何をすればいいのか
- このノウハウを実践する上での注意点
- このノウハウを実践した先に待っている未来とは
この順に説明されたKindle本を読むことで、読者はあなたのノウハウを再現できるようになれると感じてくれますから、モチベーションを維持しながら最後のページまで読み切ってくれます。
とはいえ、本は章立てで構成されていますから、この10項目を内容によって6つに分割し、6章立ての構成にしてください。
読ませるKindle本の構成
第1章:読むための動機付け
- そのノウハウを身につけた経緯は何か
- ノウハウを実践して得られるものは何か
- そのノウハウのメリット、その根拠や理由
第2章:全体像という「地図」を渡す
- そのノウハウの全体像
- そのノウハウを実行するための前提条件や必要な準備について
第3章~第5章:具体的なノウハウの解説
- まず何から取り掛かればいいのか(3章)
- 次に何をすればいいのか(4章)
- 最後に何をすればいいのか(5章)
第6章: その先に待っている未来(または、3〜5章で伝えたことをより効率的にするためのプラスアルファのノウハウ)
- このノウハウを実践する上での注意点
- このノウハウを実践した先に待っている未来とは
次に、各章ごとに構成内容を確認していきます。
第1章:読むための動機づけ
読者に対して、あなたの出版したKindle本を読む動機づけをします。
「この本は面白そうだ」「読んでみたい」思ってもらい、最後まで読み進めるためのモチベーションを維持できる内容を語ります。
あなたがこのノウハウを身につけることに至った経緯、あなたがノウハウを実践して得られたこと、実践するメリットとその根拠や理由などを述べてください。
第2章:全体像という「地図」を渡す
ノウハウの全体像を提示します。
今から何を学び、どのようなステップを踏んでゴールに至るのかを先に伝えると、読者は安心します。
読者に対して、ノウハウの全体像を見せる「地図」を渡すイメージです。
ノウハウを実践する上での前提条件や必要な準備があればここで解説します。
第3章~第5章:具体的なノウハウの解説
全体像を見せたら、次は具体的なノウハウを三つのステップで解説します。
3章〜5章の各章でそれぞれ一つずつステップの詳細を解説してください。
読者は、今自分が全体像のどの部分を学んでいるのかを理解しながら読み進められます。
第6章:その先に待っている未来
最後に、このノウハウを実践した先に待っている未来像を提示します。
次のステージで読者が得られる未来をイメージできるように話を進めてください。
あるいは、この本で学んだノウハウをより効率的に実践するためのプラスアルファの情報を伝えるのも良いでしょう。
AIを活用した原稿作成・図表作成
原稿の構成が決まったら、次は原稿の執筆に入ります。
今の時代、原稿は生成AIに書かせるのが賢い選択です。
紙ベースで商業出版をするのであれば自分で書くべきですが、Kindleの原稿執筆に多くの時間を費やすのはもったいないと私は考えています。
ただし、AIを使って原稿を書く場合には、いくつか注意点がありますので、次に挙げておきます。
AIは堂々とうそをつく
AIは間違った情報を提示することがあるので注意してください。
そのまま出版してしまうと、著者としてのあなたのブランドが傷つきます。
AIを使う場合には、ゼロから何かを生み出すツールとして使うのではなく、あなた自身のオリジナルノウハウを文章化してもらうための「言語化ツール」として使い、自身のファクトチェックが効く範囲で利用します。
AIの文章はつまらない
AIが生成する文章は、無機質でマニュアルのようになりがちです。
これを解決する裏技として、特定の人気作家をAIに憑依させる方法があります。
あまり公にはできないのですが、有名なコピーライターや人気作家などの名前を指名し、いかにもその人が執筆しているようにと指示をすると、その文体でエモーショナルに書いてくれるのです。
文章力は構成と表現力の組み合わせですから、構造化が得意なChatGPTで構成を作り、表現力が豊かな生成AIの「Claude」でリライトさせるなど、複数のAIを組み合わせるような工夫もできます。
AIは長文が苦手
Kindle本の300ページは、文字数で言うと約10万文字ほどです。
10万字を超えるような長文を一度に書かせようとすると、人間もそうですが生成AIも話が逸れたり同じことを繰り返したりします。
これはAIが備えるメモリに問題があり、10万字分の情報を蓄積しながら書き進めることができないためです。
これを避けるには、まず本の全体像をAIに理解させ、それを章や節単位に細かく分割して「この概要から逸脱しないように」と指示を出しながら、パーツごとに書かせるのがコツです。
そのパーツをつなぎ合わせれば、1冊の本として成立します。
このように、書くべき概要をガイドラインとして先に作り、そのガイドラインに沿ってAIに書かせていけば、長い文章でも生成AIに書かせることは可能です。
押さえておきたい図表生成AI
原稿だけでなく、図や表などの素材もAIに任せることができます。
まずは画像についてです。AI画像生成ツールはいろいろありますが、指示通りのイメージが出やすく加工もしやすいAIとしてお勧めしたいのが「Canva」です。
図版については、文章から自動で図解を生成してくれて使い勝手のいい「Napkin」がお勧めです。
同じ図版でも、配色やデザインのバリエーションも豊富に出してくれます。
表の生成は「Genspark」がお勧めです。
こちらが思った通りの表が出来上がってきます。
データを準備していなくても、AIがインターネット上からデータを集めてきてくれる機能もあります。
プレゼンテーションの資料も作れる優れものです。
Napkin
https://www.napkin.ai/
Genspark
https://www.genspark.ai/
感謝されるKindle本を作ろう
Kindle Unlimitedの利用者は会費を払うとKindleが読み放題ですから、⼀つひとつのKindle本にお⾦を払っている感覚はありませんので、こちらから良い内容のKindle本の提供さえできれば「無料でこんなことまで教えてくれるのか」と思ってくれます。
無料で提供されている感覚ですから、その⼈たちにとって多少でも有益な情報を渡すだけで喜んでもらえて、その上、感謝までしてもらえるのです。
AIに書かせても、感謝されるKindle本が提供できれば、その感謝をきっかけに信頼関係が構築できます。
これができると、この後に紹介するKindle本の巻末に⽤意した特典を受け取ってもらえる流れに入るのがスムーズです。
読者特典とレビュー依頼の戦略
読者特典を受け取る仕掛けは、巻末に設置する
原稿と図表が完成したら「読者特典」をプレゼントする仕掛けを作ります。
Kindle本の巻末にその特典を受け取れるURLを入れておきましょう。
Kindle Unlimitedの収益は、読まれたページ数に比例します。
そのため、読者に最後までページをめくってもらうことを目指しますから、特典請求ページの設置は本の巻末です。
紙ベースの書籍は、読まれないリスクを考えて特典請求ページを本の最初の方に置くのがセオリーですが、Kindleでは読ませることが収益化になるので考え方としては逆です。
読者特典を受け取ってもらうのと引き換えに、あなたが得るのは読者のリストです。
メールアドレス、LINEのリストがあれば、機会を作って読者との直接的な接点が持てます。
しかし読者は正直です。
魅力を感じない特典は受け取ってくれません。「ありもの」で済ますのではなく、読んでくれたKindle本のテーマに関連するものを用意して、読者に「これは絶対に欲しい」と思ってもらえるものを準備しましょう。
特典の請求方法はシンプルにしてください。メールアドレスとLINEの両方を登録させるような、複雑で不誠実な方法は避けるべきです。
メールアドレスを入れてボタンを押したのにLINEにも登録しなければ特典がもらえないというのは騙し討ち感があって、個人的には不愉快です。
自分が嫌がることは人にもしないことを、鉄則にしていきましょう。
レビュー依頼のテクニック
Amazonの規約上、特典と引き換えにレビューを依頼することは禁止されています。
ブログなど、オープンなところでレビューを依頼することは絶対にしてはダメです。
しかし、特典を受け取ってあなたに感謝の気持ちを持っている読者に対して、特典を送付する際のメールなどのようなクローズドな場で「レビューをつけていただけますと嬉しいです」とやんわりとお願いはできます。
返報性の法則も働き、レビューを書いてもらえる確率が上がります。
レビューがまったくない本よりも、レビューのある本の方が、当然ですが興味を持たれます。
人気のある本と判断されるからです。
ページをめくってもらうには人気がある本としてKindle Unlimitedの利用者の目に留まることはとても重要になります。
またAmazonのシステム(アルゴリズム)は、「売れる可能性が高い本」「人気のある本」を、自動的に顧客に勧めるように設計されていることが考えられますから、それを判断する上で、指標になるのはレビューの数と評価であることは想像できます。
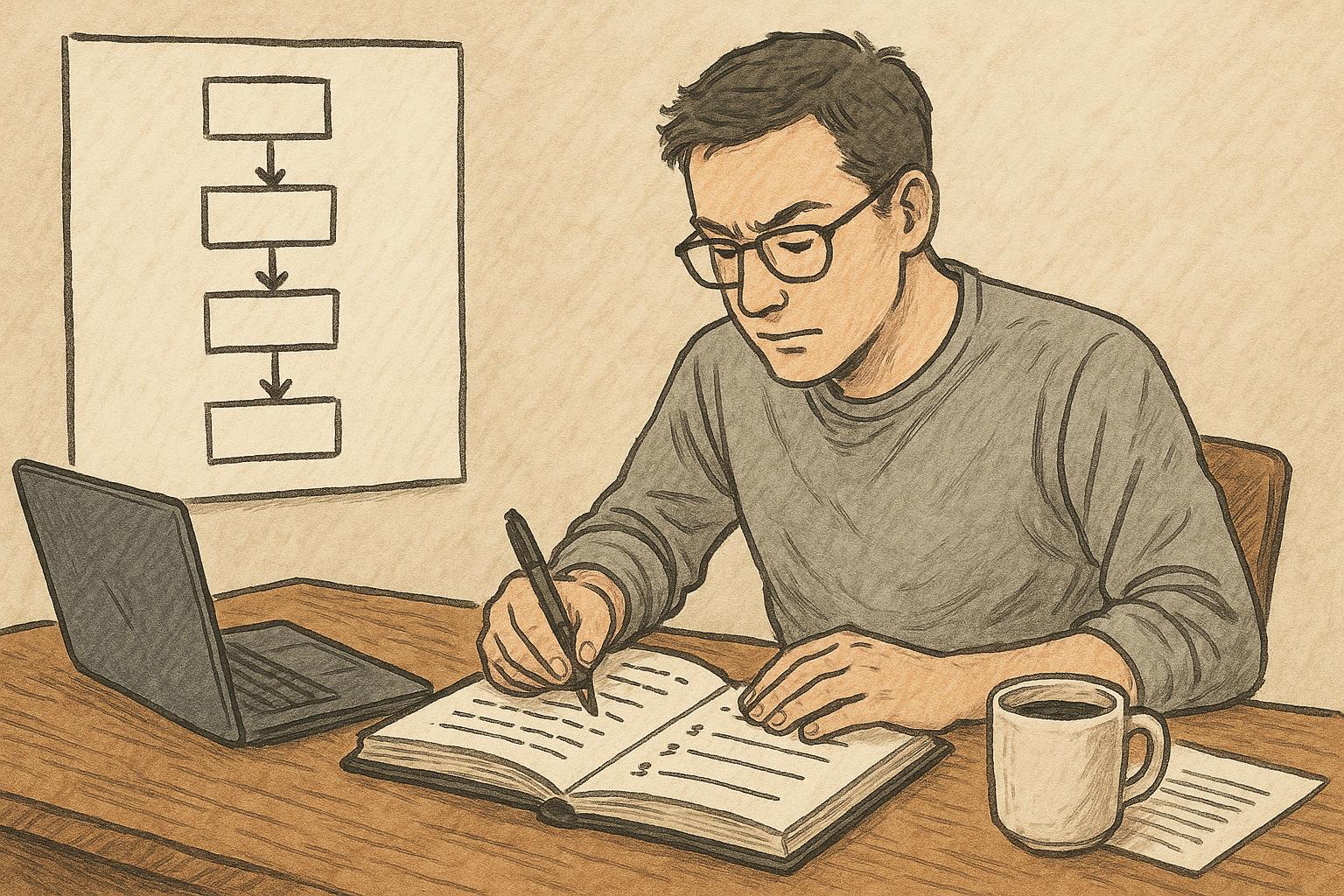
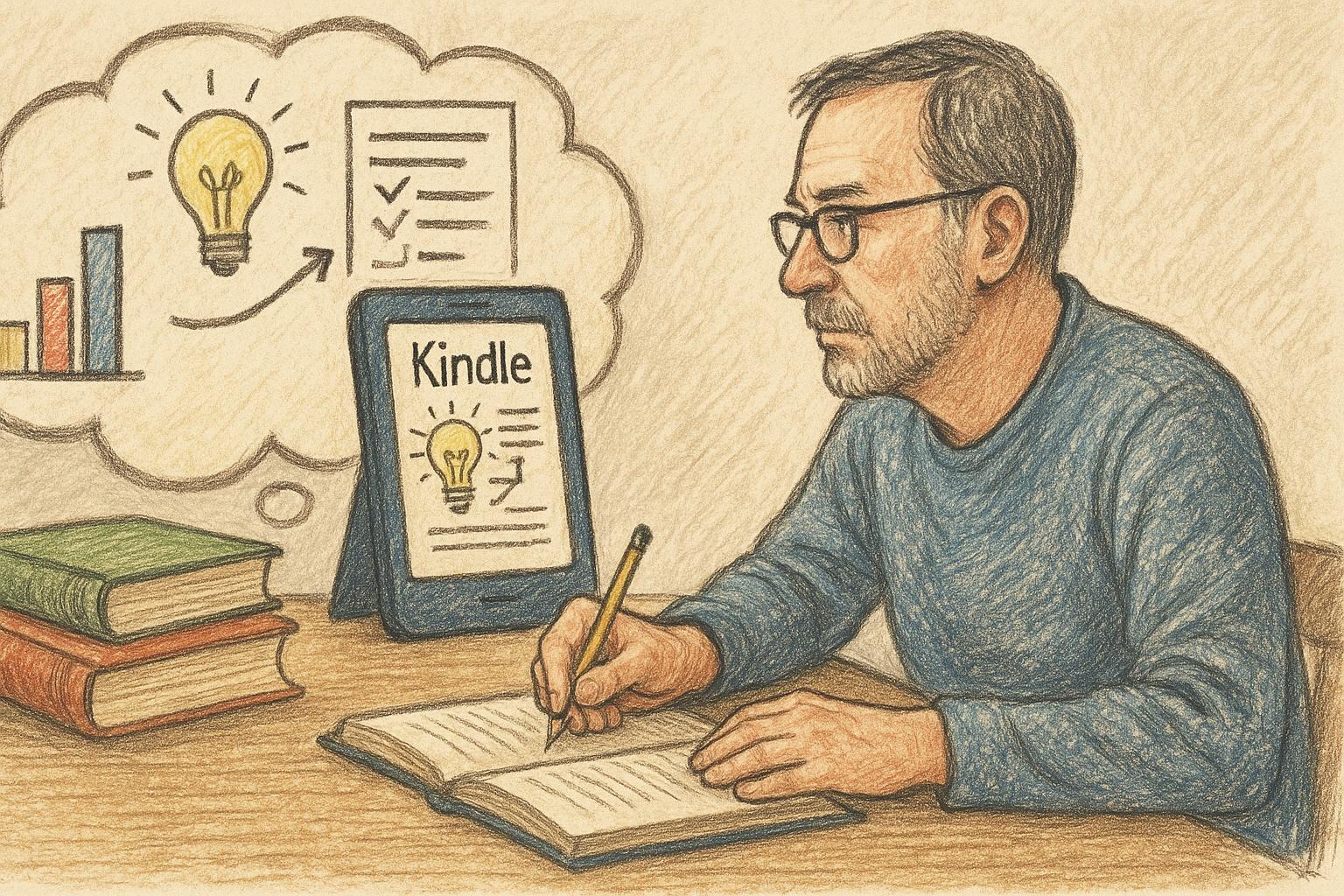
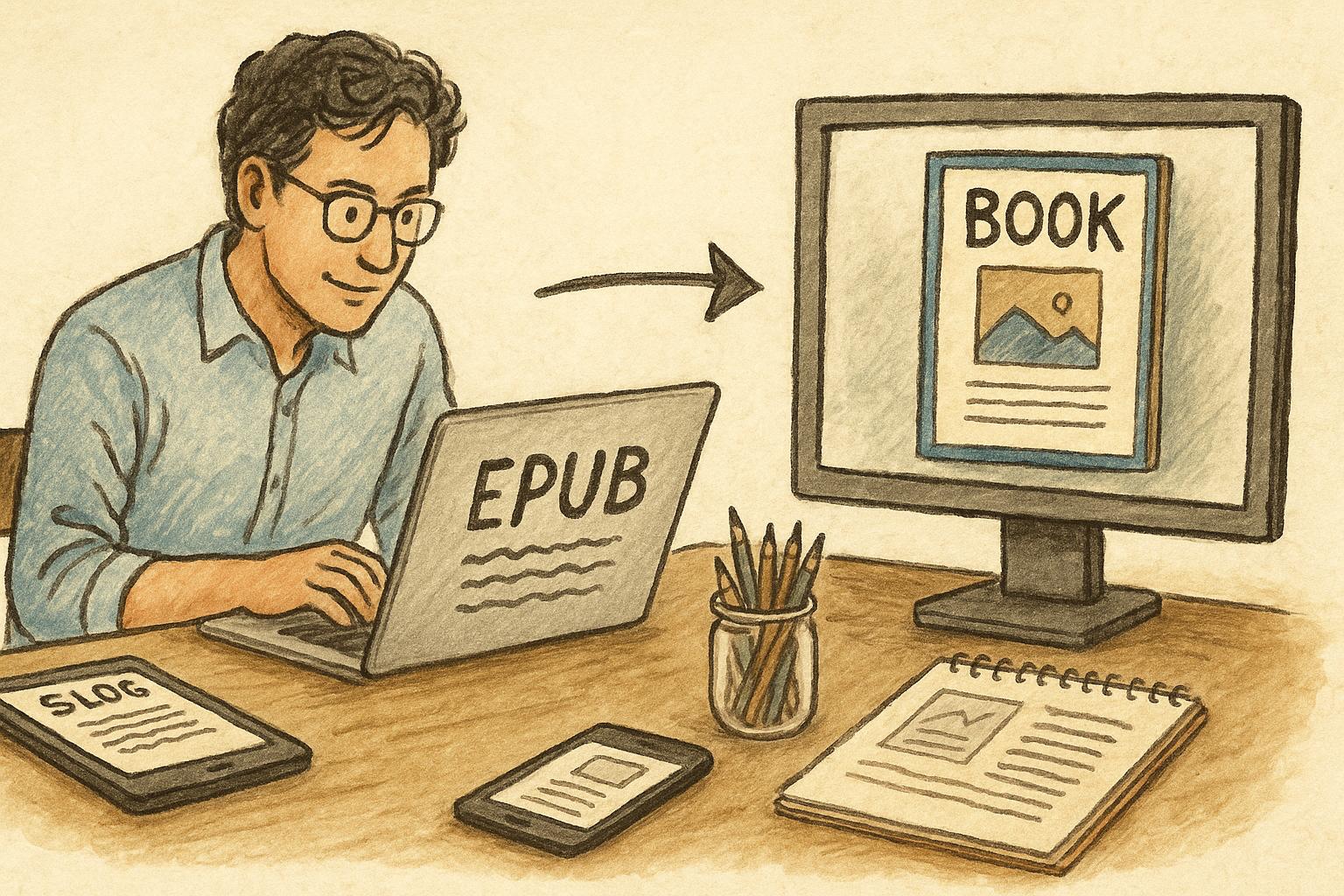
コメント